ハクビシンの移動距離と行動範囲は?【1日で最大2km移動】広範囲な対策で効果的に被害を防ぐ

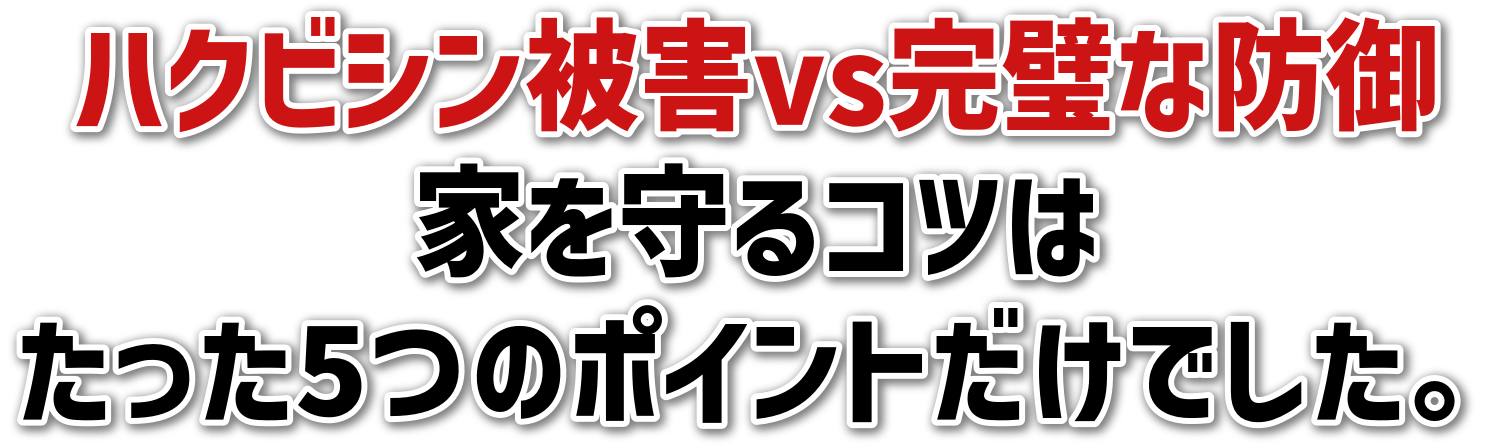
【この記事に書かれてあること】
ハクビシンの移動距離と行動範囲、ご存知ですか?- ハクビシンの1日の平均移動距離は約500mから1km
- 季節や地形によって行動範囲が変化する特徴
- 他の動物との行動範囲の比較で見えてくる特性
- 半径1km圏内を重点的に対策することの重要性
- ハクビシンの移動距離を考慮した効果的な対策5選
実は、この小さな動物、驚くほど広範囲を動き回るんです。
1日最大2kmも移動するなんて、想像以上ではありませんか?
でも、この知識が効果的な対策の鍵になるんです。
季節や地形によって変わる行動パターン、他の動物との比較、そして実践的な対策方法まで。
この記事を読めば、あなたの家や農地を守る新しいアイデアが見つかるはず。
さあ、ハクビシンの世界をのぞいてみましょう!
【もくじ】
ハクビシンの移動距離と行動範囲の実態

1日の平均移動距離は約500mから1km!最大2km移動も
ハクビシンは意外とよく動き回る動物なんです。1日の平均移動距離は約500mから1kmもあり、最大で2kmも移動することがあります。
「えっ、そんなに動くの?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、考えてみてください。
ハクビシンは夜行性の動物で、食べ物を探して歩き回るのが日課なんです。
ハクビシンの移動距離について、詳しく見ていきましょう。
- 平均移動速度:時速5kmから7km
- 1時間あたりの移動距離:約500m
- 夜間の活動時間:4〜6時間
最大2kmも移動するって聞くと、「うちの庭に来たハクビシンが、隣町まで行っちゃうの?」なんて心配になるかもしれません。
でも、そう遠くまで行くことはめったにありません。
ハクビシンは、食べ物や安全な寝床を見つけられる範囲内で行動します。
つまり、あなたの家の周りに好きな食べ物があれば、その範囲内をぐるぐる回っているだけかもしれないんです。
この行動範囲を知っておくことで、効果的な対策が立てられます。
例えば、家の周り500m圏内を重点的に対策するだけでも、かなりの効果が期待できるんです。
季節によって変化!秋は最も活発で広範囲を移動
ハクビシンの行動範囲は、季節によってガラリと変わります。特に秋は最も活発で、広範囲を移動する時期なんです。
まず、季節ごとの特徴を見てみましょう。
- 春:活動範囲が少しずつ広がり始める
- 夏:暑さを避けて、比較的狭い範囲で活動
- 秋:最も活発に広範囲を移動
- 冬:寒さを避けつつ、食料を求めて意外と広範囲を移動
実は、秋はハクビシンにとって大事な季節なんです。
冬に備えて栄養を蓄える時期だからです。
果物や木の実が豊富な秋。
ハクビシンは「よーし、おいしいものを探しに行くぞ!」とばかりに、いつもより遠くまで出かけていきます。
この時期は1日の移動距離が2kmを超えることもあるんです。
逆に夏は、「暑いなぁ。あんまり動きたくないなぁ」という感じ。
日中の暑さを避けて、涼しい夜にちょこちょこ動く程度です。
冬は意外かもしれませんが、結構動き回ります。
「寒いけど、食べ物がないと生きていけないからね」とばかりに、食料を求めて広範囲を探し回るんです。
この季節による変化を知っておくと、対策のタイミングが分かります。
例えば、秋に向けて行動範囲を広げ始める夏の終わりごろに、しっかり対策を立てておくのがいいでしょう。
地形による影響「平地vs山地」移動しやすさの違い
ハクビシンの行動範囲は、地形によってもずいぶん変わってくるんです。特に平地と山地では、移動のしやすさに大きな違いがあります。
まず、結論から言うと、ハクビシンは平地の方が移動しやすいんです。
「当たり前じゃない?」って思うかもしれませんが、実はそれほど単純ではないんです。
平地と山地それぞれの特徴を見てみましょう。
- 平地:
- 移動が容易
- 見通しがいい
- 食料が豊富
- 山地:
- 移動に体力を使う
- 隠れ場所が多い
- 食料が限られる
「あっちに美味しそうな果物があるぞ!」なんて、遠くの食べ物も見つけやすいんです。
そのため、行動範囲が広くなりがちです。
一方、山地では移動に体力を使うので、あまり遠くまで行きません。
でも、「ここなら安全そうだな」という隠れ場所を見つけやすいんです。
面白いのは、川や池の影響です。
小川程度なら「ちゃぽちゃぽ」と泳いで渡っちゃいますが、大きな川や池は避けて通ります。
つまり、大きな水辺は自然の障壁になるんです。
この地形の特徴を知っておくと、対策の立て方が変わってきます。
平地なら広い範囲に対策を施す必要がありますが、山地なら隠れそうな場所を重点的に対策するのがいいでしょう。
「うちの近くに川があるから、ハクビシンは来ないかな」なんて思っている人もいるかもしれません。
でも、油断は禁物です。
ハクビシンは意外と賢くて、橋を使って川を渡ることもあるんです。
都市部と郊外での行動範囲の差に注目!
ハクビシンの行動範囲は、都市部と郊外でも大きく違います。この差を知ると、効果的な対策が立てられるんです。
結論から言うと、郊外の方が行動範囲は広く、都市部ではより狭い範囲で活動します。
「えっ、都会の方が狭いの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、これには理由があるんです。
都市部と郊外のハクビシンの行動範囲の特徴を見てみましょう。
- 都市部:
- 行動範囲が狭い(半径300m〜500m程度)
- 人工的な障害物が多い
- 食料源が集中している
- 郊外:
- 行動範囲が広い(半径1km〜2km程度)
- 自然の障害物が少ない
- 食料源が分散している
「こっちに行きたいけど、大きな道路があって渡れないよ?」という具合です。
その代わり、ゴミ置き場や飲食店の裏など、食べ物が集中している場所があります。
一方、郊外では自由に動き回れます。
でも、「おいしいものを見つけるには、もっと遠くまで行かなきゃ」という感じで、広い範囲を移動することになるんです。
この違いを知ると、対策の立て方も変わってきます。
都市部なら、ゴミ置き場や飲食店の周辺を重点的に対策するのが効果的です。
郊外なら、広い範囲に対策を施す必要があります。
「うちは都会だから、ハクビシンは来ないよ」なんて思っている人もいるかもしれません。
でも、それは大間違い。
都市部にも意外とハクビシンはいるんです。
むしろ、狭い範囲に集中して生活しているので、一度来るとなかなか離れてくれないことも。
逆に郊外では、「広すぎて対策のしようがない」と諦めてしまう人もいるかもしれません。
でも大丈夫。
ハクビシンの好む環境(果樹園や畑など)を中心に対策を立てれば、効果的に防げるんです。
ハクビシンの行動範囲を無視した対策はやっちゃダメ!
ハクビシンの行動範囲を考えずに対策を立てるのは、大きな間違いです。効果的な対策を立てるには、ハクビシンの行動範囲を理解することが欠かせません。
「えっ、そんなに大事なの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、行動範囲を無視した対策は、お金と時間の無駄遣いになりかねないんです。
行動範囲を考慮しない対策の問題点を見てみましょう。
- 狭すぎる範囲の対策:
- ハクビシンが簡単に迂回して侵入
- 被害が続く
- 広すぎる範囲の対策:
- コストが膨大に
- 管理が行き届かない
- ランダムな対策:
- 効果が薄い
- ハクビシンの習性を無視している
逆に、広すぎる範囲に対策を施すと、お金がかかりすぎて続けられなくなってしまいます。
じゃあ、どうすればいいの?
ポイントは、ハクビシンの行動範囲を考慮した効率的な対策です。
具体的には、こんな方法がおすすめです。
- ハクビシンの主な移動ルートを把握する
- 食料源となる場所(果樹園や畑など)を中心に対策を立てる
- 半径500m?1km圏内を重点的に対策する
- 季節による行動範囲の変化を考慮して、対策を調整する
でも、ちょっと考えてみてください。
効果的な対策を立てれば、長期的には労力もコストも軽減できるんです。
ハクビシンの行動範囲を理解して対策を立てれば、「やった!ハクビシンが来なくなった!」という日も近いかもしれません。
ぜひ、賢い対策で快適な生活を取り戻してください。
ハクビシンの行動範囲と他の動物との比較
ハクビシンvsタヌキ!行動範囲は約2倍の差
ハクビシンとタヌキ、どっちが動き回るでしょうか?実は、ハクビシンの方が約2倍も行動範囲が広いんです!
「えっ、本当?タヌキの方が活発そうなのに…」って思いませんか?
でも、実際はそうなんです。
ハクビシンの行動範囲は平均で半径1〜2km。
対してタヌキは0.5〜1km程度なんです。
なぜこんなに差があるのでしょうか?
理由は主に3つあります。
- ハクビシンの方が体が大きく、より広い範囲を移動できる
- ハクビシンは木登りが得意で、立体的に移動できる
- ハクビシンの方が雑食性が強く、より多様な食べ物を求めて移動する
タヌキだったら「うーん、ちょっと遠いかな…」って諦めちゃうかもしれません。
この違いは対策を考える上でとっても重要です。
タヌキ対策で十分だと思っていても、ハクビシンには効果がない可能性があるんです。
「タヌキ対策をしたから大丈夫!」なんて油断は禁物ですよ。
ハクビシン対策では、タヌキ対策の約2倍の範囲をカバーする必要があります。
例えば、果樹園を守るなら、タヌキなら周囲500mくらいの対策で済むかもしれませんが、ハクビシンなら1kmくらいの範囲を考えないといけないんです。
覚えておいてくださいね。
ハクビシン対策は、タヌキ対策の倍!
これを忘れずにいれば、より効果的な対策が立てられますよ。
ハクビシンvsアライグマ!遠距離移動力に驚きの差
ハクビシンとアライグマ、どっちが遠くまで移動するでしょうか?答えは、アライグマなんです!
なんとアライグマは、ハクビシンの約1.5倍の距離を移動しちゃうんです。
「えー!アライグマってそんなに動き回るの?」って驚いちゃいますよね。
実は、アライグマの行動範囲は平均で半径2〜3km。
対してハクビシンは1〜2kmなんです。
じゃあ、なぜこんなに差があるのでしょうか?
主な理由は3つあります。
- アライグマの方が体力があり、長距離移動に適している
- アライグマはより広範囲の環境に適応できる
- アライグマの方が好奇心が強く、新しい場所を探索する傾向がある
この違い、対策を考える上でとっても大事なんです。
ハクビシン対策で十分だと思っていても、アライグマには効果がない可能性があるんです。
「ハクビシン対策をしたから大丈夫!」なんて油断は禁物ですよ。
アライグマ対策では、ハクビシン対策よりも広い範囲をカバーする必要があります。
例えば、家庭菜園を守るなら、ハクビシンなら周囲1kmくらいの対策で済むかもしれませんが、アライグマなら1.5kmくらいの範囲を考えないといけないんです。
でも、安心してください!
ハクビシン対策をしっかりやっていれば、アライグマ対策の土台にもなるんです。
ただ、より広い範囲で、より強力な対策が必要になるってことですね。
覚えておいてくださいね。
アライグマ対策は、ハクビシン対策の1.5倍!
これを忘れずにいれば、より効果的な対策が立てられますよ。
ハクビシンvs野良猫!意外な行動範囲の大きさ
ハクビシンと野良猫、どっちの行動範囲が広いと思いますか?実は、野良猫の方が断然広いんです!
なんと、ハクビシンの約3倍もの範囲を移動するんです。
「えっ!猫ってそんなに遠くまで行くの?」って驚いちゃいますよね。
実は、野良猫の行動範囲は平均で半径3〜6km。
対してハクビシンは1〜2kmなんです。
では、なぜこんなに差があるのでしょうか?
主な理由は3つあります。
- 猫はより機敏で、素早く長距離を移動できる
- 猫は縄張り意識が強く、広い範囲をパトロールする
- 猫は単独行動が多く、自由に動き回れる
この違い、実は大事なんです。
ハクビシン対策だけしていても、野良猫による被害は防げないかもしれません。
「ハクビシンさえ来なければ大丈夫!」なんて油断は禁物ですよ。
野良猫対策では、ハクビシン対策の3倍の範囲をカバーする必要があります。
例えば、庭の植物を守るなら、ハクビシンなら周囲1kmくらいの対策で済むかもしれませんが、野良猫なら3kmくらいの範囲を考えないといけないんです。
でも、心配しないでください!
ハクビシン対策と野良猫対策には共通点もあるんです。
例えば、フェンスを高くしたり、忌避剤を使ったりするのは両方に効果があります。
ただ、野良猫対策の方がより広範囲で、より細かい対策が必要になるってことですね。
覚えておいてくださいね。
野良猫対策は、ハクビシン対策の3倍!
これを忘れずにいれば、より効果的な対策が立てられますよ。
そして、両方の対策をしっかりやれば、庭や家周りをもっと守れるようになりますよ。
ハクビシンvsネズミ!家屋内での行動範囲を比較
ハクビシンとネズミ、家の中ではどっちが広い範囲を動き回るでしょうか?実は、意外にもハクビシンの方が家屋内での行動範囲が広いんです!
「えっ、小さいネズミの方が隅々まで入り込めそうなのに…」って思いませんか?
でも、実際はそうじゃないんです。
ハクビシンは家全体を利用しますが、ネズミは限られた範囲で活動する傾向があるんです。
じゃあ、具体的にどんな違いがあるのか見てみましょう。
- ハクビシン:
- 屋根裏から1階まで家全体を利用
- 広い空間を必要とする
- 家の外と内を行き来する
- ネズミ:
- 主に壁の中や床下など、狭い空間で活動
- 巣から半径10m程度の範囲で生活
- ほとんど家の中だけで完結
一方、ネズミは「壁の中の巣から台所まで、いつもの道をコソコソ行こう」って感じです。
この違い、対策を考える上でとっても大切なんです。
ネズミ対策で十分だと思っていても、ハクビシンには全然効果がないかもしれないんです。
「ネズミ対策をしたから大丈夫!」なんて油断は禁物ですよ。
ハクビシン対策では、家全体を守る必要があります。
例えば、屋根や外壁の隙間をふさぐ、換気口に金網を取り付けるなど、家の外周全体に気を配る必要があります。
一方、ネズミ対策は壁の穴をふさいだり、床下や台所周りを重点的に対策したりするのが効果的です。
でも、安心してください!
ハクビシン対策をしっかりやっていれば、ネズミ対策にもなるんです。
家全体をしっかり守れば、小さなネズミも入れなくなりますからね。
覚えておいてくださいね。
家の中のハクビシン対策は、家全体を守る!
これを忘れずにいれば、ネズミ対策も含めて、より効果的な対策が立てられますよ。
ハクビシンvsイタチ!夜間の行動パターンの違い
ハクビシンとイタチ、夜の活動パターンはどう違うでしょうか?実は、両方とも夜行性ですが、活動のピークタイムが違うんです!
「えっ、夜行性なら同じじゃないの?」って思いますよね。
でも、実際はこんな感じなんです。
- ハクビシン:
- 活動のピークは日没後2〜3時間
- 夜中から明け方にかけても活動
- 1日の活動時間は約6〜8時間
- イタチ:
- 活動のピークは真夜中
- 夜明け前にもう一度活発に
- 1日の活動時間は約4〜6時間
一方、イタチは「みんなが寝静まった真夜中が狩りのチャンス!」って感じなんです。
この違い、対策を考える上でとっても重要なんです。
イタチ対策の時間帯だけ気をつけていても、ハクビシンには効果がない可能性があるんです。
「夜中だけ注意すればいいや」なんて油断は禁物ですよ。
ハクビシン対策では、日没直後から夜明けまでの長い時間帯をカバーする必要があります。
例えば、センサーライトを設置するなら、日没後すぐに作動するようにしないといけません。
一方、イタチ対策なら、真夜中と夜明け前に重点を置いた対策が効果的です。
でも、安心してください!
ハクビシン対策をしっかりやっていれば、イタチ対策の時間帯もカバーできるんです。
ただ、より長い時間、警戒が必要になるってことですね。
覚えておいてくださいね。
ハクビシン対策は、日没後すぐから夜明けまで!
これを忘れずにいれば、イタチ対策も含めて、より効果的な対策が立てられますよ。
夜の長い時間、しっかり守ることで、庭や家を両方の動物から守れるようになりますよ。
ハクビシンの移動距離を考慮した効果的な対策5選

半径1km圏内を重点的に!防護柵の適切な設置範囲
ハクビシン対策の要、それは半径1km圏内を重点的に守ることです。これがハクビシンの行動範囲を考えた防護柵の適切な設置範囲なんです。
「えっ、そんなに広い範囲を守らないといけないの?」って思いますよね。
でも、ハクビシンの1日の平均移動距離が500mから1kmだということを思い出してください。
つまり、この範囲をしっかり守れば、ほとんどのハクビシンの侵入を防げるんです。
では、具体的にどんな対策をすればいいのでしょうか?
ここでは3つのポイントをお伝えします。
- 高さ2m以上の丈夫な防護柵を設置する
- 柵の下部を地中に30cm程度埋め込む
- 柵の上部を内側に45度の角度で曲げる
「よーし、これで安心だ!」って思えますよね。
でも、注意点があります。
半径1km全てを囲むのは現実的ではありません。
そこで、重要なのがハクビシンの侵入経路を予測することです。
例えば、果樹園や家庭菜園がある方向を重点的に守るといった具合です。
「うちの庭は小さいから大丈夫」なんて思っていませんか?
それは危険です!
ハクビシンは意外と広範囲を動き回るので、油断は禁物。
隣家や近所と協力して対策を立てるのも良いアイデアです。
覚えておいてくださいね。
半径1km圏内を重点的に、そして侵入経路を予測して効率的に防護柵を設置する。
これがハクビシン対策の基本なんです。
500mおきの対策で侵入経路を遮断!移動を制限
ハクビシンの移動を効果的に制限するには、500mおきに対策を講じるのがおすすめです。これで侵入経路をしっかり遮断できるんです。
「500mって、けっこう近いんじゃない?」って思いますよね。
でも、これには理由があるんです。
ハクビシンの1日の平均移動距離が500mから1kmだということを思い出してください。
つまり、500mおきに障害物を置けば、ハクビシンの自由な移動を大きく制限できるんです。
では、具体的にどんな対策をすればいいのでしょうか?
ここでは3つの方法をご紹介します。
- 忌避剤の設置:ハクビシンの嫌いな匂いのするスプレーを500mおきに吹きかける
- 音声装置の配置:ハクビシンが嫌う高周波音を発する装置を500mおきに設置
- 光による威嚇:動きを感知して点灯するセンサーライトを500mおきに取り付ける
「よし、これでハクビシンの侵入を防げるぞ!」って気分になりますよね。
でも、注意点があります。
ハクビシンは賢い動物なので、同じ対策を続けていると慣れてしまう可能性があります。
そこで大切なのが、定期的に対策の位置や種類を変えることです。
例えば、今月は忌避剤、来月は音声装置、その次の月は光による威嚇、というように変えていくんです。
これで「おや?いつもと違う?」とハクビシンを混乱させることができます。
「500mおきなんて、広すぎて管理が大変そう...」なんて思っていませんか?
大丈夫です!
隣近所と協力して対策を分担すれば、負担も減りますし、より広い範囲を守ることができますよ。
覚えておいてくださいね。
500mおきの対策で侵入経路を遮断し、定期的に方法を変える。
これがハクビシンの移動を制限する効果的な方法なんです。
半径2km以内の「食料源マップ」作成で効果アップ!
ハクビシン対策の効果を劇的に上げる秘訣、それは半径2km以内の「食料源マップ」を作ることです。これで、ハクビシンの行動パターンが手に取るように分かるんです。
「えっ、2kmも?そんな広い範囲まで見る必要があるの?」って思いますよね。
でも、ハクビシンの1日の最大移動距離が2kmだということを思い出してください。
つまり、この範囲内の食料源を把握すれば、ハクビシンの行動をほぼ予測できるんです。
では、どうやって「食料源マップ」を作ればいいのでしょうか?
ここでは、3つのステップをご紹介します。
- 地図の準備:お住まいの地域の地図を用意し、中心に自宅を置きます
- 食料源の特定:半径2km以内にある果樹園、家庭菜園、ゴミ置き場などをマークします
- 季節ごとの更新:果物や野菜の収穫時期に合わせて、マップを定期的に更新します
でも、注意点があります。
この「食料源マップ」は、あなた一人で作るものではありません。
ご近所や地域の方々と協力して作るのがポイントです。
なぜなら、より正確で包括的な情報が得られるからです。
例えば、「うちの裏庭にある柿の木、毎年ハクビシンに狙われるのよ」なんて情報も、マップに反映できますよね。
こういった地域の皆さんの生の声が、マップの精度を高めるんです。
「2km圏内なんて、広すぎて大変そう...」なんて思っていませんか?
大丈夫です!
最初は自宅周辺から始めて、徐々に範囲を広げていけばいいんです。
地域の方々と協力すれば、意外とすぐに完成しちゃいますよ。
覚えておいてくださいね。
半径2km以内の「食料源マップ」を作り、地域で情報を共有する。
これがハクビシン対策の効果を大きく上げる秘訣なんです。
きっと、あなたの地域のハクビシン対策が、ぐっとレベルアップしますよ!
行動範囲内に「忌避植物ゾーン」を戦略的に配置
ハクビシン対策の新しい味方、それが「忌避植物ゾーン」です。ハクビシンの行動範囲内に戦略的に配置すれば、自然な方法で侵入を防げるんです。
「忌避植物?そんなのあるの?」って思いますよね。
実は、ハクビシンが苦手な植物がいくつかあるんです。
これらを上手に活用すれば、庭をおしゃれに演出しながら、ハクビシン対策もできちゃうんです。
では、どんな植物を使えばいいのでしょうか?
ここでは、5つの忌避植物をご紹介します。
- ラベンダー:強い香りがハクビシンを遠ざけます
- ローズマリー:鋭い香りが苦手なようです
- ミント:清涼感のある香りも効果的
- マリーゴールド:独特の香りがハクビシンを寄せ付けません
- ニーム:インドセンダンという木で、虫除けにも使われます
「よーし、これでおしゃれな庭になるし、ハクビシンも来なくなるぞ!」って感じですね。
でも、注意点があります。
忌避植物だけでは完璧な対策にはなりません。
あくまで総合的な対策の一部として活用するのがポイントです。
例えば、忌避植物ゾーンと防護柵を組み合わせたり、センサーライトと一緒に使ったりするんです。
こうすることで、より効果的にハクビシンを遠ざけられます。
「植物の世話、面倒くさそう...」なんて思っていませんか?
大丈夫です!
これらの植物は比較的丈夫で、手入れも簡単です。
むしろ、庭の景観が良くなって一石二鳥ですよ。
覚えておいてくださいね。
ハクビシンの行動範囲内に忌避植物ゾーンを戦略的に配置する。
これが自然で効果的なハクビシン対策なんです。
きっと、あなたの庭がもっと素敵になり、同時にハクビシンも寄り付かなくなりますよ。
超音波装置の効果的な設置!行動範囲の境界線に注目
超音波装置、実はハクビシン対策の強力な武器なんです。特に、ハクビシンの行動範囲の境界線に設置すると、驚くほど効果的です。
「超音波?人間には聞こえないの?」って心配になりますよね。
大丈夫です。
この装置が出す音は人間の耳には聞こえません。
でも、ハクビシンにとっては、とっても不快な音なんです。
では、どうやって効果的に設置すればいいのでしょうか?
ここでは、3つのポイントをお伝えします。
- 境界線の特定:ハクビシンの行動範囲の端、つまり半径1〜2km付近に設置
- 侵入経路の予測:果樹園や家庭菜園がある方向を重点的にカバー
- 複数台の連携:約50m間隔で複数台設置し、死角をなくす
「よーし、これで安心だ!」って思えますよね。
でも、注意点があります。
超音波装置は効果的ですが、ハクビシンが慣れてしまう可能性もあるんです。
そこで大切なのが、定期的に周波数や設置場所を変えることです。
例えば、今月は16kHzの周波数、来月は18kHzに変える。
または、今月は庭の東側、来月は西側に移動する。
こうすることで、「あれ?いつもと違う?」とハクビシンを混乱させ続けられるんです。
「超音波装置って高そう...」なんて思っていませんか?
確かに初期投資は必要ですが、長期的に見ればとてもコスト効果の高い対策です。
電気代も少なく、維持費もほとんどかかりません。
覚えておいてくださいね。
ハクビシンの行動範囲の境界線に超音波装置を設置し、定期的に変化をつける。
これが効果的なハクビシン対策の一つなんです。
きっと、あなたの地域のハクビシン被害が、ぐっと減ることでしょう。